Femtech_037国立大学法人大阪大学

取り組むべき課題
本事業が取り組む課題は、更年期に伴う多様な心身の不調が「見えにくく、相談しにくい」まま我慢されやすい点です。症状の個人差や日内変動も大きく、情報が断片的で支援につながりにくい現状があります*1。働く世代では就労・家事・育児・介護が重なり、症状の波で勤務調整や受療判断が難しく、支援が後回しになりやすい課題があります。事業特性として、企業・地域の実証フィールドでは、任意参加と同意、プライバシー保護、勤務配慮、測定環境、産業保健・地域医療との連携、効果指標と評価設計が課題です。また、地域資源の差によるアクセス格差や再測定・フォローの導線設計も課題です。
*1 厚生労働省「更年期症状・障害に関する意識調査(基本集計結果)」2022年。
今回の実証事業の内容
今回の実証では、おでこに貼るパッチ式脳波計で睡眠の質や状態を短時間で把握し、専門家との面談で生活習慣(休養・食事・運動・ストレス対処)を一緒に整理します。必要に応じて再測定や記録で経過を確認し、気づきとセルフケアの継続を支援します。個人の結果は同意に基づき適切に管理し、企業へは集計した傾向のみを共有します。医療行為ではなく、働く世代の方が無理なく続けられるサポートを提供します。症状負担・勤務のしやすさ・幸福度への影響を匿名の指標で評価し、職場での配慮やセルフケアを考える材料にします。
この事業で貢献できること
今回の実証では、睡眠脳波と面談により「いまの状態」と優先すべき生活行動を可視化し、本人の気づきと実行を促します(短期)。記録と必要時の再測定で自己管理が定着し、症状負担や勤務のしづらさの軽減、幸福度の向上をめざします(中期)。匿名集計の知見は、地域の早期相談体制や医療機関の適切受療につなぐ導線、企業の就労配慮ガイドライン整備に役立ち、生産性と定着向上に貢献します(中長期)。成果は症状負担・勤務のしやすさ・幸福度を指標に評価します。また、得られた知見は実装ガイドの整備とエビデンスの蓄積に資します。
現在の製品・サービスの提供状況
(2025年8月時点)
サービス提供者
国立大学法人大阪大学
実証を通じて提供している
サービス名Pitaスクリーニング 更年期症状
令和7年8月時点のサービス状況
実証中
サービス概要
睡眠脳波の計測と専門家面談を組み合わせ、働く世代の更年期における「いま」の状態と優先すべき生活行動を可視化する支援サービスである。おでこ貼付のパッチ式脳波計で睡眠の質や状態を把握し、面談で整え方を提案する。協力企業の職域で実証し、個人情報は同意に基づき適切に管理、企業へは匿名・集計で共有する。評価指標は症状負担、生産性、幸福度等とし、職場の就労配慮づくりに資する。大阪大学とPGVの知見を基に開発した、気づきとセルフケアを支える非医療の伴走型支援である。地域・医療機関・産業保健と連携し、実装手順と評価枠組みを整備する。
サービス導入先・利用者
〇法人等組織向けサービス
〇女性向けのサービスのみ対象としている法人の性質や
サービスの対象者の目安〇健康保険組合
〇規模不問
①健康経営・女性活躍を推進する企業
②交替制・夜勤のある職場(製造・医療等)
③働く世代のプレ更年期~更年期の女性サービスのURL
サービスの問い合わせ窓口となる
メールアドレス
事業体制の紹介
| 代表団体 | 国立大学法人大阪大学 |
|---|---|
| URL | https://www.osaka-u.ac.jp/ja |
| 参加団体 | PGV株式会社 |
※実施体制は2025年8月31日時点で確定しており、掲載を希望した団体を記載

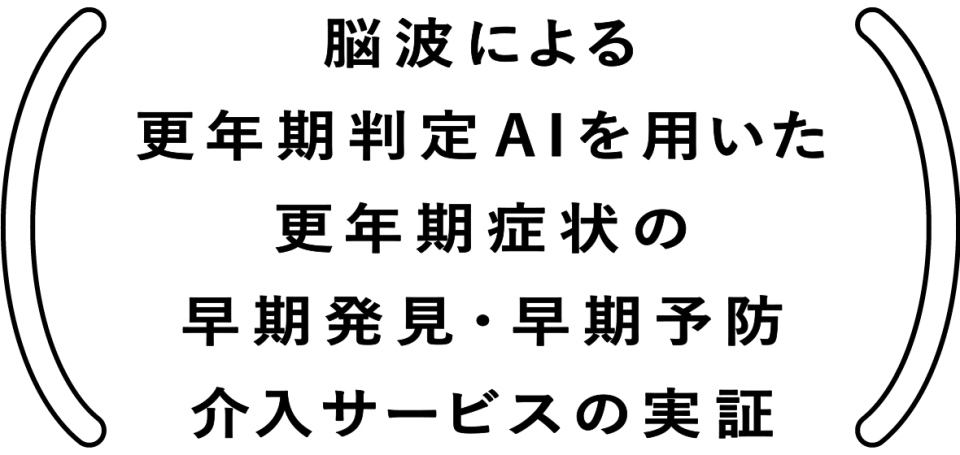
事業のご担当者から
ひとこと
国立大学法人大阪大学/澤田 健二郎さん
本実証は、更年期の不調が見えにくく相談しづらい現状を変えるため、睡眠脳波と専門家面談を組み合わせ、気づきとセルフケアの第一歩を支援する取組として立ち上げました。働く世代の就労配慮や適切な受療の導線、職場で続けやすい支援の形を検証します。企業の人事・産業保健、自治体、医療機関、保険者の皆さまと協働し、評価指標の整備と現場実装を進めたいと考えています。女性のウェルビーイングと就労継続、生産性や定着率の向上に資する仕組みづくりに共に挑戦してくださる仲間とつながりたいです。